半額忠臣蔵
朝露の巻
「ヤアヤア、遠からん者は音に聞け、近くばよって目にも見よ。
我こそは源頼光公が後裔、浅野弾正小弼長政なるぞ、
我と思わんものはいざ組まん、いざ組まん。」
浅野内匠頭長矩は浅野長政の子孫である。浅野長政は豊臣秀吉の
妻、寧々の妹婿。 その縁で取り立てられた彼は五奉行筆頭として活躍、
関ヶ原の戦いでは東軍につき、その功績で子の幸長は大大名として紀伊の
国に封ぜられた。 その幸長の弟が赤穂浅野家の祖、長重である。
「ヤアヤア、遠からん者は音に聞け、近くばよって目にも見よ。
我こそは源頼光公が後裔、浅野采女正長重なるぞ、
我と思わんものはいざ組まん、いざ組まん。」
長重の子が長直、長直の子が長友である。そしてその子が内匠頭長矩である。
「ヤアヤア、遠からん者は音に聞け、近くばよって目にも見よ。
我こそは源頼光公が後裔、浅野内匠頭長直と、浅野采女正長友と
浅野内匠頭長矩なるぞ、我と思わんものはいざ組まん、いざ組まん。」
浅野長政は戦国時代の武将であり、浅野長重は大坂の陣にも出陣している。
しかし、長直以降は戦もなく、戦場に出ることはなかった。何がいざ組まん、か。
いわば一人相撲である。
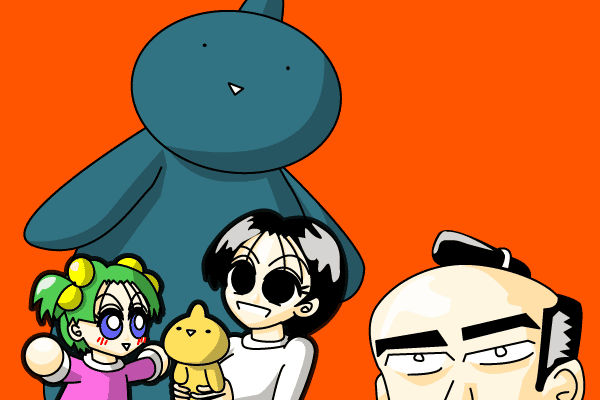
「いざ組まん、いざ組まん。」
そもそも源平時代ならいざしらず、「ヤアヤア遠からんものは…」などと言う名乗りを
あげたりするものは戦国時代にはいない。戦場は日々進化しているのである。
昨日の常識が今日にはもう非常識である。当時、足軽は頭にかぶった鉄傘を鍋に
していた。現在このようなことをする足軽などを諸兄は見られたことはないであろう。
ことほどさように物事は日進月歩、男子三日逢わざれば渇目して見よ。なのである。
浅野内匠頭長矩には、この辺がよくわかっていなかった。物事はすべて有為転変。
伝統を重んじる勅使饗応役といえども、この世の中の流れが無関係であるわけは
なかったのである。将軍綱吉の生母今日も江戸城書院で儀式の練習をする内匠頭の
悲鳴が聞こえてくるのであった。
「内匠頭殿。そこは違う。」
「ど、どちらでございましたかな。」
「上上下下右下上っ。下右右下下右下右っ。」
「こ、こう…。」
「ええい歯がゆいっ!それでも大名かっ!」
「で、でも…。」
「泣くなっ!」
小藩とはいえ内匠頭はれっきとした大名。家中でこれほどまでに厳しく指導されることは
なかった。三十五歳の目にも涙である。
「まったくこれだから田舎侍は…。」
「うみゅう…。」
内匠頭の小刻みに震える肩に、ぽんと手が置かれた。後ろには誰もいるはずがないのに。
真っ赤な目で振り返ると、そこには上品な笑みを浮かべる老人がいた。
「まあまあ、そう一度にぽんぽん言われても、覚えきれるものではないじゃろう。
内匠頭殿も一生懸命なのじゃ。それをお助けするのが、我ら高家の仕事ではないかの、
飛騨守殿。 」
「しかし上野介殿…御勅使到着までもう幾日もないのですぞ、急がねば、どのような失態を犯す
か…。 」
そう聞くと、老人はゆかいそうに笑った。
「ほっほっほ、まだ若いの、飛騨守殿。」
「は。」
「御勅使饗応役に選ばれる大名の候補はいくらでもおる。それがなぜ、内匠頭殿になったか。
そこを考えられぬようでは、まだまだ高家肝煎の座は遠いの。 」
飛騨守は唇をかんだ。先ほどまで内匠頭を怒鳴り散らしていた畠山飛騨守則安といえど、高家
の筆頭、高家肝煎の吉良上野介義央の前では子供のようなものであった。 内匠頭のほほは
思わずゆるんだ。
「何がおかしい、内匠頭殿。」
「いえ…」
上野介は飛騨守を目でとがめると、手にした扇子をぽんぽんとたたきながら飛騨守の周りを歩き
だした。
「よいかの、はるばる京から江戸まで下ってこられる御勅使が一番求めておられるのは何か、
わかるかの。 」
「それはやはり、儀礼を尽くしての饗応こそ…」
ち、ち、ち、と上野介は舌を鳴らした。
「そのようなことは当然のことじゃ。これまでも礼をつくして、贅をつくして、できうる限りのことを
してきたのじゃ。じゃがの。それでは足らん。 」
「足らぬと、おおせられると…。」
「それは御勅使のことを考えれば自然と出てくるものじゃ。」
「御勅使のことを…。」
「御勅使となられる公家衆は普段はずっと狭い京の中で暮らしておられる。当然ながら外界の
ことなどまったくご存じない。それだけに外界の情報に飢えておられるのじゃ。我ら高家が京に上っ
た折に、江戸のことなどを根掘り葉掘り聞かれるであろうが。」
「それは確かに。私も毎度難儀しております。」
「そこじゃ。」
ぽん、と扇子が飛騨守の頭の上で鳴った。
「御勅使もはるばる江戸まで来られて京に帰られた時には当然ながら、公家衆中の注目の的じゃ。
江戸や道々のことを根掘り葉掘り聞かれる。その時に、「つつがなく儀式も終わりました、たいへん
結構でした。」などと言うてみい。「なんだその話は。」「もう少しネタを仕込んでおけ。」「オチは。」と
非難ごうごうじゃ。御勅使殿は「はるばる江戸まで行って面白くない公家」言う評価に落ち着いて
しまうであろう。」
「はあ…。」
「よいかの、飛騨守殿。」
上野介の唇が、飛騨守の耳元にささやく。
「御勅使を、「面白くない公家」にしてしまっては、我ら高家の面目丸つぶれなのじゃ。」
「はあ…。」
「御勅使に、江戸の土産話となる面白エピソードを提供するのが、我らの役目なのじゃ。
そのために必要なのがハプニングじゃ。面白ハプニングを起こすのが、最高の饗応と、
なるであろうの。 」
上野介と内匠頭の目が合う。こくり、と内匠頭はうなずいた。内匠頭の耳は赤く、熱を持っていた。
松の廊下の刃傷の、数日前のことである。

(了)